圧電型センサの概要
圧電効果
出力信号をより高品質なものにするため、PCB社のセンサは圧電効果を利用しています。("圧電"を表す"piezoelectric"の"piezo"とは、ギリシア語で"圧力をかける"という意味があります)圧電素子に外部から力が加わると、力に比例して分極します。図1は、天然の圧電素子である水晶の結晶に外力が加わった結果、分極した様子を示しています。
Si+はシリコン原子、O-は酸素原子です。水晶は感度が高く、かつ安定しているため、優れた圧電素子として利用されます。
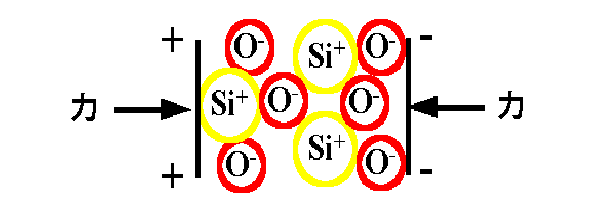
PCB社のセンサには、水晶だけでなく人工結晶であるセラミックも利用されています。セラミックは高電界処理を行うことによって、高品質な圧電素子として利用できるようになります。この特性は、ノイズをできるだけ低減する必要のある測定システムでは理想的です。水晶、およびセラミックの長所/短所を表1に示します。
表1: 圧電素材の比較表
| 水晶 | セラミック |
|---|---|
| 天然の圧電素材 | 人工の圧電素材 |
| 高い電圧感度 | 高い電荷感度 |
| 鉄鋼と同程度の剛性 | 形状に自由度がある |
| 優れた長期安定性 | 540℃まで使用可能 |
| パイロ電気効果が少ない | パイロ電気効果が多い |
| 温度変化に強い | 特性が温度で変化する |
圧電型センサには、様々なサイズ、形状の圧電素材が利用されます。図2 に圧電型センサの主な構造を3種類、示しました。それぞれの構造に長所・短所があります。(赤は圧電素材を示しており、矢印は、センサに対してどのように圧力がかかるかを示しています。また、一般的に加速度計にはマス(おもり)があります。これはグレーで示しています。センサ構造の詳細については、次章で詳しく説明します。)圧縮型には高い剛性があるため、高周波での圧力/力センサの構造に適しています。圧縮型の欠点は、温度変化に敏感であるということです。ビーム型は構造が単純ですが、使用可能な周波数レンジが狭いことと、耐衝撃性が低いという欠点があります。シェア型(せん断型)は、広い周波数レンジで使用可能、低い横軸感度、ベース歪みからの影響が少ない、温度変化による影響が少ないなどの長所があることから、加速度計の構造として広く使用されています。
図2:材料の組合せ
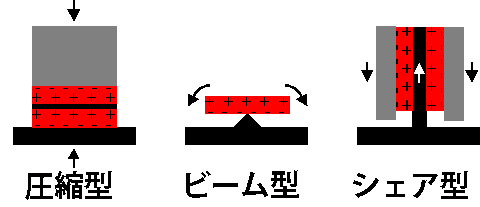
圧電材の弾性係数は15×106psi(104×109N/m2)と、多くの金属と同等で、非常に小さな歪みで高い出力が得られます。言い換えるならば、センサ用の圧電素子は、歪みがほとんどない固体とみなして良いということです。このため、圧電型センサは非常に丈夫であり、測定レンジの広い範囲で優れた線形性を持っています。実際、正しく設計されたシグナルコンディショナと組み合わせて使用することで、一般的な圧電型センサのダイナミックレンジは120dBのオーダーにもなります。これは、1つの加速度計で、0.0001gから100gまでの加速度を測定できるということを意味します。
圧電材について重要な事として、圧電型センサは、動的な現象/変化する現象のみを測定できる、ということがあります。慣性誘導、大気圧、質量などの連続的な静的現象は測定できません。静的現象にも初期値による出力信号がありますが、これは圧電材またはセンサ内蔵の回路に起因する時定数によって徐々に減衰します。この時定数は一次のハイパスフィルタに一致しており、デバイスの静電容量および抵抗により決まります。このハイパスフィルタにより、低周波側のカットオフ周波数もしくはデバイスの測定限界が決まります。
構造
代表的な力センサ、圧力センサ、加速度センサの例を図3に示します。(グレーはセンサが取り付けられる構造体を示しています。)青は、センサのハウジングを示しています。圧電材である水晶は赤で示しています。黒の電極には、(黄色で示される微小回路において電圧に変換される前の)電荷が蓄積されています。加速度計には緑で示されるマス(おもり)も含んでいます。どのセンサも内部構造に大きな違いはありません。振動を測定する加速度計では、水晶と、センサが取り付けられている構造体の振動により、既知マス'M'に力が加わります。これにより、水晶にかかる力はニュートンの運動の第2法則であるF=MAの式で簡単に計算できます。圧力センサと力センサの動作原理はほぼ同じで、圧電材である水晶にかかる外部圧力を元にしています。大きな違いは、圧力センサは圧力を集めるためにダイアフラムを使用している点です。
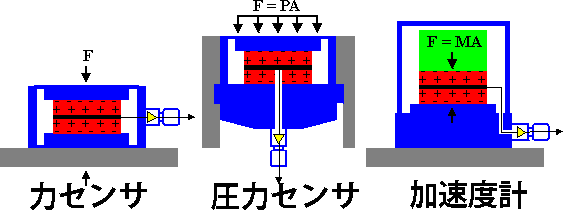
図3: センサの構造
センサはその動作原理が似ているため、特定のパラメータ測定用に設計されたセンサであっても、他の入力に対して反応します。測定対象でない入力に対する感度を下げることで、目的のパラメータをより正確に測定できるようになります。たとえば、最先端の圧力センサは補正エレメントを利用して加速度の感度を低下させます。他のセンサでは、熱補正回路によってセンサの熱係数を低下させます。加速度計については、シェア型(せん断型)の構造にすることにより、熱の影響、横軸感度、ベース歪の影響を低下させています。
シグナルコンディショニング
センサからの出力信号は、オシロスコープ/レコーダ/その他の収録器で解析を可能にするため、適切な状態に調整する必要があります。図4に示すように、信号の調整方法には2種類あります。
(1)センサに信号調整のためのアンプ(微小回路)を内蔵する
(2)調整機能を"ブラックボックス"化してセンサの外に置く (PCB社はアンプを内蔵したセンサをICP®として登録しています。アンプを内蔵していないセンサは電荷出力型センサと呼んでいます)
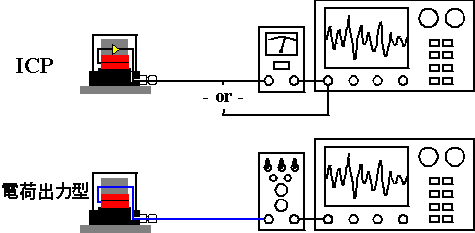
図4: センサシステム
どちらの調整方法も次の3つの処理をアナログ回路で行っています:
1. 扱いやすい低インピーダンスの電圧信号に変換する →2. 信号を増幅/減衰させる →3. フィルタリングする
センサシステムが正しく機能するためには、回路の位置が重要です。上記(1)(2)の方法について、詳細を以下に示します。
はじめに、ICP®型センサについて説明します。このコンセプトは1967年に発明されて以来、多くの改良が加えられてきました。回路が小型化され、回路コンポーネントの価格が下がり、集積回路や超高抵抗素子の小型化によって信号処理機能は向上しました。しかし、"シンプルに使いやすく"という発明当初からの趣旨は変わっていません。この2線システムでは、一本を電源信号として、もう一本をグランド信号として使用します。内蔵回路は、センサのタイプによって電荷増幅型か、電圧増幅型のどちらかとなります。この回路が稼働するための電源は、18~30VDC、2mAの定電流電源です。(価格、使いやすさ、その他の機能は別にして、定電流電源の機能を信号収録器に内蔵か、外付けかで技術的な差はありません。)システムの詳細を図5に示します。
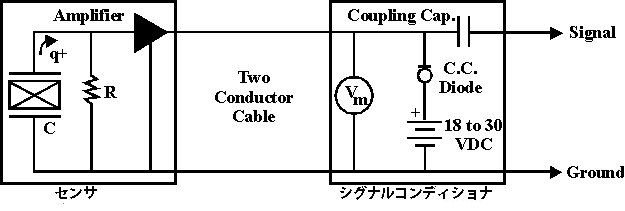
図5: ICP® センサシステム
このシステムの特長は以下の通りです:
(1) 内蔵アンプは、ほとんどの収録器が対応可能な低インピーダンスの電圧信号を生成する
(2) シンプルかつ使いやすい定電流電源のみが必要である。これにより、1チャンネルあたりのコストが低減できる
(3) 信号は、厳しい環境下であっても品質を損なうことなく長いケーブルで送ることができる
(4) 回路の動作温度限界は一般的に121℃までである(ケースによっては154℃まで対応可能)
(5) 一般的な2線の同軸ケーブルもしくはツイスト・ペアケーブルが使用可能
(6) センサの特性(感度と周波数レンジ)はセンサ内部で決まっており、電源からは独立している。
次に、電荷出力型センサについて説明します。電荷出力型センサは機械的にはICP®センサと同じセンシング構造を持っています。大きく異なる点は、信号調整のための回路がセンサの外付けになっていることです(これをチャージアンプと呼んでいます。)
これは、最初の圧電型センサが開発された1950年代はまだ集積回路を小型化する技術がなかったためです。高性能な外付けのチャージアンプは正しく操作するのが難しい上に、一般的に非常に高価なものです。(代わりに、低価格のインライン型チャージコンバータが主流になってきました。)
今日では、電荷出力型センサはアンプ内蔵型のセンサが使えないような温度環境でのみ使用されます。
電荷出力型センサを使用するシステムでは、以下の通り様々な利点と欠点があります:
(1) センサからの出力は高インピーダンス信号であるため、収録器へ送る前に調整が必要である。
(2) 高性能なチャージアンプ、インラインのボルテージフォロワなどの外付けのシグナルコンディショナが必要である。
(3) 高インピーダンス信号は、ケーブルを動かす、電磁ノイズややラジオ波などの環境の影響により品質が低下する。
(4) アンプが外付けであるため、センサの種類によっては540℃までの動作が可能である。
(5) ローノイズケーブルが必要である。
(6) センサの特性(感度と周波数レンジ)は、外付けのシグナルコンディショナの設定によって変更できる。
まとめ
圧電型センサは、他のセンシング技術では見られない独自の機能があります。アプリケーションにより、「広い周波数レンジとダイナミックレンジを持つ」事が利点となり、また「静的な現象を測定できない」という事が欠点となります。センサ、センシング技術を選択する際は、性能に関する仕様を慎重に検討する必要があります
こちらもあわせてお読みください。
各種圧電型センサ一覧は、こちらから。